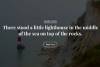ガレージブランドに観る民藝 前編

コラムのページを開いていただきありがとうございます。
記念すべき第一回ということで、今回は前編・後編に分けて、私の創作活動の原点とも言うべきアウトドアギアと民藝品についてご紹介したいと思います。
民藝品とアウトドアギアは同じ道具でも全然別の分野かと思いますが、ひも解いていくと特にガレージブランドのギア(以下ガレージギア)と民藝品は非常に近いスタンスで作られているのではないかと考えるようになりました。
さらに、民藝品について調べるうちに「道具の在り方」や「自身のものづくりの姿勢」などを考えるきっかけにもなりました。
愛され続ける道具とは、ものとは、どんなものなのか。
今回は、ガレージギアと民藝品の共通点を探りながら、ものと共に生きる在り方についても考えていきたいと思います。
前編では民藝とはどのようなものかを掘り下げ、後編ではガレージギアと民藝品の関係についてご紹介します。
時間が無い方は後編から読んで頂いても結構です。
はじめに
「機能美」
アウトドアギアを語る上では必ずと言って良いほど出てくるキーワード。
なぜなら、便利な日常から離れて「不便を楽しむ」アクティビティがアウトドア。
そんなシーンで使うギアだから機能的でないといけない。
その無駄の無い姿の美しさを「機能美」と呼んでいます。
私は、アウトドアギアとは?と聞かれたら「機能美に溢れた道具」と答えます。
アウトドアメーカーから発表されたもので無くとも、アウトドアで使いやすいと思う道具はアウトドアギアと言えるでしょう。
むしろベテランになればなるほど、様々なジャンルの道具をアウトドアギアとして取り入れている気がします。
自分にとって使いやすいギアを選んだり、自作したりすることもアウトドアギアの楽しみの一つ。
気温・天候・場所などの様々な条件が常に変化する自然の中で、自身が選んだ道具たちがどれほど機能するのか。
それによりどれだけ快適に過ごすことができるのか。
そして使うことでどんな感情が満たされるのか。
とてもワクワクしますね。
この感情は「持っていける道具は有限」という縛りがあるからこそ成り立ちます。
だからこそ選び抜かれた道具が生きるんですよね。
そんな選び抜かれた道具たち。
皆さんの普段の相棒たちには共通点や仲間に加える条件はありますか?
これからご紹介する民藝には「最も長く愛され続ける道具とはどんなものなのか」というひとつの解釈が示されています。
ぜひ自身の身の周りにある道具を想像しながら読んで頂ければと思います。
民藝について
まずは今回のキーワードである民藝についてご紹介していきましょう。
民藝という言葉は、哲学者の柳宗悦さんが中心となって作った言葉。
工藝の一分野として「工芸品の中で最も深く人間の生活に交わる領域」と定義しています。

つまり「普段使いするもの、どこにでもあるもの」であり、安価で親しみやすいものを指します。
衣食住に直結し、当たり前のように使うものなので、その形は質素で頑丈。
そして形や模様は単純であると言われています。
また民藝品であることの条件として、以下の基準を設けています。
全ての基準に100%当てはまる品は少ないように感じますが、なんんとなくどんなものかは想像できそうですね。
わたしは最初に聞いた時、職人さんが仕事に使う工具を想像しました。
仕事で使うので、頑丈で使いやすくないといけないのかなと。
みなさんはどんなものを思い浮かべましたか?
民藝の祖
柳宗悦とは
ではこのような考えを思いつき、普及させることに奔走した柳宗悦さんとはどんな人物だったのでしょうか?
美術評論家と宗教哲学者であり、大学教授でもある柳は、1889年に東京府麻布区(現東京都)に誕生しました。
そして72歳の生涯を終えるまで、素晴らしい友人達の助力のもと、国内外の民藝品の美しさを普及させるために様々な取り組みを行ったと言われています。
学習院高等科に在学中、陶芸家のバーナード・リーチの協力で、同人雑誌「白樺」を創刊。
宗教学や美術に関する記事を執筆しました。

そんな中、イギリスの詩人で画家のウィリアム・ブレイクとの出会いで得た「美しさの見極めは直観力」との考えが柳の「芸術と宗教」という思想の基礎を作り、当時の「新しい美しさ」の発見に繋がったようです。
また、柳は弟子にも直観力の重要性を説き「目に入るもの全ての作品を瞬時に批評」するトレーニングをさせたと言います。
その後、磁器研究者の浅川伯教が手土産で持参した朝鮮の工藝品を見て興味が沸き、頻繁に朝鮮を訪れるようになりました。
作品はもちろんのこと、織物や民家の完成度なども高く評価したそうです。
そして1924年にはソウルに、李朝時代の無名作家の手による日用品を展示した「朝鮮民族美術館」を設立。
民藝品を通して、芸術家ではなく名もなき職人たちの新しい社会的価値を提示しました。
さらに、国内では工藝や民藝運動に関する著書を多数発表。
その一つである雑誌「民藝」を創刊し、民藝運動の母体となる「日本民藝協会」を設立しました。
そして、1934年には柳自身が初代館長を務めた「日本民藝会館」を創設し、国内の民藝品の展示も行いました。
その後も沖縄や台湾などの南西諸島の文化保護にも尽力し、「文化功労者」(日本において文化の発達向上に特に功績顕著な者に与えられる称号)に認定。
韓国からも、文化の発展を通して国家の発展に寄与した功績を称えられ「宝冠文化勲章」を授与されています。
もともと陶芸作家との関わりが深かった柳は、蚤市などで雑多に扱われている皿や器などの「名もなき骨董品」に民藝の心を見出しました。
(正確には骨董品は古い道具の事を指しますが、民藝品は新古に関しての定義はありません。ただ柳曰く、美しいものは過去の物が多いと語っています。)

当時は現代に比べて個人で作れるものも今より少なく、評価できるジャンルにも限りがあったように思います。
民藝品としての基準は設けても、作品の年代や種類を規制しなかった柳。
もし柳が現代に生きていたら、様々なものに民藝の心を発見し、新しい価値を見出してくれたのではないかと思います。
美術と工藝の関係
民藝運動に生涯を捧げた柳ですが、その道は苦難の連続だったようです。
柳の生きた1900年当時の「美」は貴族階級が好んだ「個人主義の芸術(Art)」が基準となっており「大衆的な工藝(Craft)」はその下位に位置付けられていました。
確かに美しいものを見た時に「芸術的だ!」とは言いますが「工芸的だ!」とは言いませんよね。
そのため、近代の名作品と言われるものには以下の3つの基準があると柳は説き、分類することで、美術の「美」と工藝の「美」を整理しようと考えました。
柳曰く
個人主義的なものの中に、実用的なものが少ない事は歴史が物語っている。
美を「個性の表現」に留めておくのは狭い考えなのではないか。
という事が民藝運動の主張でした。
そして宗教学者としての研究でたどり着いた「我執」に基づく考えから、工藝にしか無い「美」を語っています。
優劣をつけるものでは無いのでしょうが、これくらい主張しないと埋もれてしまうほど当時は新しい考え方であったのかも知れません。
確かに貴族階級が愛し、歴史も長い芸術に対して、工藝との格差が生まれてしまったのは納得できます。
ただ柳は、民藝運動を通して「美の基準は一つでは無く、それぞれにしか無い美しさを見出してほしい」と伝えたかったのでは無いでしょうか。
「誰も目を向けなかったことに価値を見出した」柔軟さと、その考えを文化として定着させた柳の行動力には脱帽です。
恐らく柳宗悦は、民藝品のような「用の美」を体現した人物であったのかも知れません。
工藝の分類
では最後に工藝の分類についてお話しして、前編を終えたいと思います。
民藝は工藝の一分野と先に書きましたが、他にも幾つかに分類することが出来ます。
18世紀半ばから、19世紀にかけて起こった産業革命以降、工藝は「機械工藝」と「手工藝」に二分されました。
機械製品は商業的な目的に特化した考えに基づき製作されていたため、品質の悪い軟弱な品も出回ってしまいました。
そのため、ひとつひとつの素材に自らの手で触れながら、道徳心と労働の悦びをもって作られた手工藝こそ工藝の本意である。と柳は語っています。

また、手工藝の中でも「貴族的工藝」と「民衆的工藝」に二分されます。
貴族的工藝は「工藝界の美術品」と称されるように、材料・技術・装飾・色彩の全てを凝らして贅沢を極めた高価なもの。
それに対し民衆的工藝品、すなわち民藝品は衣食住に直接必要な質素なもので、最も使いやすいように形づくられたものと定義されました。

この分類からも、民藝品は「最も庶民の生活に近いもの」だとわかります。
民藝とは国民の生活を反映する道具ということ。つまり「最も国民的な道具」と言えるでしょう。
さらに柳は「国民的な作品ほど、普遍的なものはない」とも語っています。
時代が変わって、使うものに変化があっても人間的な生活を送る上では、本質的なことは変わらない。
最も長く愛され続ける道具とは、民藝品なのかも知れませんね。
最後に
いかがでしたでしょうか。
民藝や工藝について考えるうちにガレージギア以外にも、現代にもその意思を受け継ぐものが沢山あるのではないかと思うようになりました。
例えばお洒落な雑貨や家具、昨今の高級なキャンプギアは「貴族的工藝品」に分類できるかもしれません。
どの分類が良い悪いということでは無く、その道具が「どんな分類」で「どれが自分に合うのか」がわかることが重要だと思います。
機械製品全てが悪いとは思いませんし、贅沢な品を作った背景には民藝に通じる思想があったかもしれません。
ものづくりを通して民藝と出会い、また少し世の道理を学べた気がします。
いつの時代も、向き合い方は変化しても、道理は普遍的であると思いたいですね。