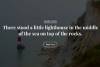ガレージブランドに観る民藝 後編

それでは、「ガレージブランドに観る民藝 後編」ということで本コラムの確信部分をご紹介していきます。
前編では民藝について深く掘り下げましたが、後編はガレージブランドのギア(以下ガレージギア)と民藝の共通点、そしてものとともに生きる在り方について考えて行きたいと思います。
後編からご覧いただいている方も、お時間のある時にぜひ前編もご覧ください。
前編のおさらい
まず前編の内容である民藝について簡単にご説明します。
民藝とは、哲学者の柳宗悦さんを中心に作られた言葉。
アート作品や豪華な工藝品が、名作と言われていた時代の新しい価値観として「名もなき職人の作った使うための道具」の美しさを広めたいという想いから生まれました。
つまり「道具の中で、最もシンプルで我々に近い道具」というところでしょうか。
そんな「使用することに特化した、手作りの道具」とガレージギアは大切にしている部分が近いのではないかと思うのです。
そして私は、この共通点こそガレージギアの在り方なのではないかと感じています。
「現代の民藝品」とも言えるガレージギア。
では、そんなガレージギアを開発するガレージブランドとはどんなブランドを指すのでしょうか?
まずは少しだけガレージブランドについてご紹介しましょう。
ガレージブランドとは
たくさんのアウトドアブランドがある中で、近年よく耳にする「ガレージブランド」という言葉。
読んで字のごとく、自宅のガレージのような小規模スペースで個人単位の開発を行うブランドのことを言います。

アウトドアブランドの中でも最小単位の領域がガレージブランドと言えるでしょう。
どこまでがガレージブランドか?というような、組織の規模のような線引きは難しいと思います。
ただ「ガレージブランドにしかできないこと」はたくさんあるような気がします。
面白いことにどんなブランドも、最初はガレージブランドの規模からスタートしています。
例えば世界のトップアウトドアブランド「patagonia(パタゴニア)」の創業者であるイヴォン・シュイナードは、ブランドを始めたころはクライミングをする際の岩場に打ち込むギア「ピトン」を自身の工房で手作りで製作し、ヨセミテ国立公園で露店を開き、手売りをしていたのは有名な話。
他にも、世界をけん引しているアウトドアブランド「THE NORTH FACE(ノースフェイス)」の創業者であるダグラス・トンプキンスはサンフランシスコの小さなアウトドアショップを起点にブランドを成長させました。
また、ベストセラー素材「AZTEC(アズテック)」を開発してトップアウトドアブランドの地位を獲得した「macpac(マックパック)」の創業者であるブルース・マッキンタイヤーは、若干19歳で両親に借りた2000ドルの資金を元手に、自宅のガレージで自作のバックパックを作り始めたところがスタートだったそうです。
小さいからこそできること。
それはしがらみが少なく「自身の個性を最大限に発揮できる」ことが根本にあるように感じます。

大衆に受け入れられなくても良いからこそ、狭く深いギアを作ることが出来る。
一番のユーザーでもあるブランドオーナー自身が使いやすく、そのアイテムを使う事で今まで得られなかった感動を感じることができる。
また、荒削りな部分はあれど、期待や不安など様々な感情を抱えながら「作りたい」というピュアな情熱のもと作られたギア。
そんな、「純度の高いギア」こそがガレージブランドのギアだと私は思います。
ガレージブランドに観る民藝
前編では、どんなものが民藝品として当てはまるのかという基準を9つ挙げました。
わたしはガレージギアもその基準に近い道具なのではないかと感じます。
それでは、ひとつひとつ見ていきましょう。
1:観賞用ではなく使うために作られた「実用性」
機能美という言葉があるように、アウトドアギアは機能性が高いギアだが、ガレージギアは突出した機能を持つ。
2:名もなき職人によって作られた「無銘性」
ガレージギアのステータスは、作者が有名かどうかよりも「機能的」かどうかが重要。
3、手仕事によってたくさんつくられたであろう「複数性」
ガレージギアはハンドメイドの範囲内だが製品としての量産は行う。
4:誰でも購入が可能な価格の「廉価性」
庶民が買えない金額ではありません。大切にしたいと思える価格。
5:反復によって得られる技術を有した「勤労性」
私も縫製工場でミシンの修行を行いましたが、技術の向上とともに作れる範囲も広がった。
6:地域に根付いた独自の形状である「地方性」
作者の経験がダイレクトに反映されるガレージギアは文化に根付いた形状。
7:効率生産のため工程毎に専門職が行う「分業性」
デザイン・生産はブランドで行うが、材料は専門業者に頼む。
8:先人が編み出した技術の積み重ね「伝統性」
先人のギアをリスペクトを込めて研究する。そして自身の引き出しとして取り入れ、組み合わせることでオリジナリティが生まれる。
9:自然の恵みなどの目に見えない支え「他力性」
ガレージブランドを立ち上げた全ての人は、自然からの恩恵を受けていると思われる。
先に民藝品を「使用することに特化した、手作りの道具」と述べました。
もともとアウトドアギアは「機能美」が基礎にある道具なので、使用することに特化した道具とも言えるでしょう。
むしろ現代でここまで機能美に溢れた道具はなかなか無いのではないでしょうか。

ガレージ単位の生産であれば、私のように自らミシンを踏んで在庫を製造するので、民藝品の「手仕事」という部分も共通しています。
また、ガレージギアは単純で洗練された形態のギアも多く、修理のしやすいデザインなども、使い続けることを念頭に置いた民藝品との近しさを感じます。
さらに「アウトドアで使う道具」という特性から、インスピレーションは自然の中から頂いたものが多い気がします。
柳の言う民藝品とは
道具の中で我々に一番近しい存在ゆえ、一番の働き手である。毎日当たり前のように使うため、丈夫で健康的に作らている。そのため、健全な肉体と魂を宿した逞しい道具。
それに対しガレージギアは
多機能では無いかも知れないが、正しい使い方をすれば必ず我々の助けになってくれるもの。
純粋に作者が体験した感動をもとに「使いやすさ」を追い求めた道具。
どのような想いで作るかにより、設計や材料・どこで作るかも変わります。
子は親の鏡という言葉がありますが、作品は作り手の等身大を映す鏡と言えるでしょう。
私は、民藝品もガレージギアも一番大切にしているのはその精神性。
それが作品にダイレクトに反映されているように感じます。
つまりどちらも「雑念が無く、シンプルな情熱のもと生まれた道具」
そして、この共通点を備えた道具こそ「最も長く愛され続ける道具」
又は「長く愛したい道具」なのではないでしょうか。
そんな道具との生活は、ささやかですが、身近に感動が溢れている暮らしに繋がると私は感じています。
みなさんの身に回りにはどんなものがありますか?
ものとともに生きる
それでは最後に「ものとともに生きる」ことについて考えて終わりたいと思います。
「ものを大切にできる人は人も大切にする」という言葉がありますが、私は道具と深く関わるようになってから一層実感する機会が増えました。
私自身、昔は今よりも余裕がなく、いろいろなことを後回しにしてしまっていました(もちろん今でもあります)がそんな時は、自分も含めて大切にできるものが少なくなってしまっていたように思います。
私は山に登って感動したときはいつも「この一瞬を大切にできている」という実感があります。
そういう実感がある出来事はずっと忘れないので非常に価値があるひとときですよね。
「その一瞬一瞬が感動にあふれている」それがアウトドアの素敵なところだなと感じています。
ただ、見方を変えれば普段の生活にもそんな一瞬はあるのではないでしょうか。
ものや人、時間、そして自分。
大切にできるものが増えれば選択も変わってきます。
大切にしたいから大切に選びたい。
ものが溢れる現代で、自分らしく生きていくことは大切にできるものを知る。
つまり「自分を知って受け入れる」ということなのかも知れませんね。
あとがき
いかがでしたでしょうか?
今回のような文章を書くのは生まれて初めてなので、つたない内容だったかも知れませんが、最後までお付き合い頂きありがとうございます。
コラムは不定期更新ですが、今後も投稿していきたいと思っておりますのでよろしければお立ち寄りくださいませ。